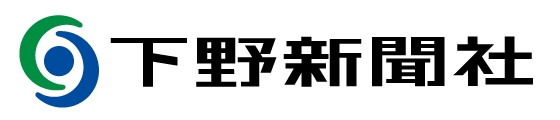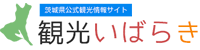《食しる》大子のこんにゃく 伝統的特産品 見た目は無骨、実は繊細

おでんやみそ田楽、煮物などでおなじみのこんにゃくは奥久慈の特産品。その原料となるコンニャク芋は古くから大子町などで栽培されている。

コンニャク芋
こんにゃくは、インドシナ半島原産とされサトイモ科のコンニャク芋から作られる。茨城では古くから奥久慈地域を中心に水はけのよい傾斜地を利用して、コンニャク芋が栽培されてきた。凍(し)みこんにゃくは奥久慈特有の気候を利用する伝統的保存食。冬の寒空の下、薄く切ったこんにゃくを天日に干し、水をまき夜に凍結、昼に解凍を繰り返して作られる。
大子町こんにゃく生産協会会長を務める菊池常勝さん(68)はコンニャク芋を専門に、約7ヘクタールを栽培する大規模農家。同会では、畑の生育状況を見る品評会や先進地である群馬県への研修などを行っている。
1年目は、春に「生子(きご)」と呼ばれる親指ほどの大きさのものもある芋を植え、秋にこぶし大ほどに育つ。それを保存し、再び春が巡ってくると植え、秋に約1キロの大きさになると収穫、出荷できる。「出荷できる大きさに育つまで2、3年かかる。肥大が小さかったらさらにもう1年」と菊池さん。町内と、全国一の生産量とシェアを誇る群馬県に出荷される。行き先は粉の原料業者。10月半ばから12月半ばまでが収穫時期。機械で土をふるいながら芋を掘り起こす。大きさを選別して、畑で芋の泥を一つ一つ落としていく。
コンニャク芋はごつごつした無骨な見た目と違って繊細な作物。「雨が多いと根腐れしてしまう。深く溝を掘り、水はけをよくする。雨が少なすぎてもだめ。干ばつや高温にも弱い」と栽培の苦労を語る。寒さに弱く傷みやすいため、7度に設定された貯蔵庫で保管するという。
■精粉
県北地域の農産物直売所で、農家の人が生芋をすりおろして作った玉こんにゃくが売られているのを見かける。刺し身こんにゃくで食べると、とろっとした歯触りが楽しめる。
現在、市販されているこんにゃくの多くは、生芋を加工した粉から製造する。現在の粉こんにゃく製法の始まりを作った立役者が常陸大宮市諸沢出身(現在)の中島藤右衛門(1745~1825年)。
藤右衛門を祭る大子町の蒟蒻(こんにゃく)神社縁起などによると、江戸時代中期、生芋は重く傷みやすいために長距離の輸送や保存が難しかった。貯蔵する方法を探していた藤右衛門は偶然から芋を乾燥させて粉にする方法を発案。苦心の末薄く輪切りにした芋を串に刺して天日で乾燥させた「荒粉(あらこ)」をひき「精粉(せいこ)」にする粉こんにゃくの製法に成功した。生芋よりも軽量化が図られ、輸送や保存がしやすくなり、販路を拡大した。こんにゃくは水戸藩の専売品として藩の財政を支えたとされる。
現在のこんにゃく業界の基礎を築いたともいえる精粉加工だが、県大子蒟蒻原料協同組合理事長の松浦幹夫さん(72)は「昭和50年代には町内に15軒あった加工業者が、今では2社だけになった」。全国の組合でも40社足らずという。
■商品開発
菊池さんが会長を務める奥久慈大子こんにゃくの会は2018年、品質向上や販路拡大、産地のブランド化などを推進するために町内の生産者や加工、製造業者などで設立された。こんにゃく粉を利用した商品開発に取り組み、試行錯誤して、こんにゃくスムージー、わらびもち風こんにゃく、こんにゃくパンが出来上がった。会員でもある松浦さんは「消費者に産地と認識されることで商品価値が上がれば」と期待を寄せる。
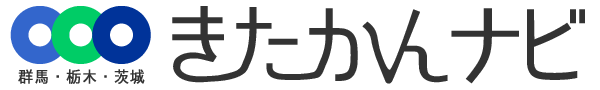 北関東を感じる観光情報サイト
北関東を感じる観光情報サイト