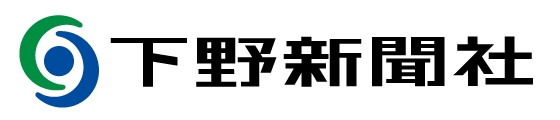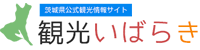《食しる》かんぴょう ユウガオの実、むいて乾燥 肉厚で歯触り楽しめる 結城

巻きずしや昆布巻きなどに使われる県西地域特産のかんぴょう。その素材や成り立ちは意外と知られていない。全国一の生産量を誇る栃木県の隣、結城市の農家や専門問屋を訪ねた。
乾物のかんぴょうは、ウリ科のユウガオの実から作られる。漢字で書くと「干瓢」。夏の強い日差しを利用して、手間暇かけて作られてきた。
結城市の農業、吉田栄さん(62)は妻と長男と家族で、かんぴょう作りを行う。「父親の代から60、70年かんぴょうを作ってきた。子供のころから手伝っていた」と話す。「高齢化と安い外国産に押され、うちの地域の生産者は数えるほどに減ってしまった」
■夏の風物詩
吉田さんは3月下旬にユウガオの種をまき、4月に定植。白い花が咲き始めるころは人工授粉を行い、その後は自然交配に任せる。今年は実が収穫できるようになった6月下旬からかんぴょう作りが始まった。順調なら9月上旬まで続くが、7月の雨の影響で8月20日ごろにシーズンを終えた。「天候に左右されるが、例年は暑い時季に75~80日ぐらい続く重労働。家族が協力しないとできない」
暑さを避け、夜明け前に作業を開始する。下に膨らんだ形の実は重さ10キロほどで、大玉スイカより大きく見える。皮は薄緑色で果肉は白い。実を逆さにして心棒に刺し、回転させながら刃を当て、幅5センチほどの帯状にむいていく。2メートル50センチから3メートル弱の長さにそろえ、さおに掛け、ハウス内に干す。白いすだれのような光景は夏の風物詩。 「ハウスや乾燥機が入るようになって、天気が多少悪くても(ユウガオの)玉さえあれば作業できるが、乾き具合に影響する」と天候を気にしながら、最低でも3日かけて製品にするという。

白さが際立つ、かんぴょう干し
乳白色で肉厚なかんぴょうが出来上がると、仲買人が仕入れにやって来る。吉田さんが「庭先卸」と呼ぶ昔ながらの取引で、仲買人は買い入れた製品を結城市や栃木県内の問屋に卸す。
■専門問屋
結城の歴史編さん委員会編集「結城の歴史」(1995年発行)によると、かんぴょうはもともと栃木県で栽培が始まり、茨城で栽培されるようになったのは1890年代から1900年代に入ってからとある。同市では栃木県から江川村(現結城市)の村民が種苗を手に入れ、同村を中心に栽培農家が増えていったという。
結城市にある桜井長太郎商店は県内で数少ないかんぴょう専門の問屋。明治時代に魚問屋として創業、大正時代にかんぴょうも扱うようになり、昭和に入り専門問屋となった。
同商店代表で4代目の桜井守さん(88)は55年ごろから問屋の仕事に携わる。「昔は農家の貴重な現金収入だった。新治(現筑西市)や境、総和(現古河市)など県西地域で作られていたが、だんだん野菜作りに変わっていった」
同商店では結城市産と栃木県産をデパートや乾物店などに卸すが、「結城みやげにしたい」と直接買いに来る人も多く、全国からも注文が入る。
妻のいねさん(86)は「卵とじやみそ汁といった和の料理だけでなく、自分の味を主張しないかんぴょうは、どんな料理にもなじむ。歯触りも楽しめる」と味付けは自在だ。
日本食品標準成分表2015年版(七訂)によると、ゆでたかんぴょうは100グラム当たり28キロカロリー、食物繊維5.3グラム、カルシウム34ミリグラムなどが含まれており、「健康食品としても人気が高い」と桜井さん夫妻は話した。
| 地図を開く | 近くのニュース |
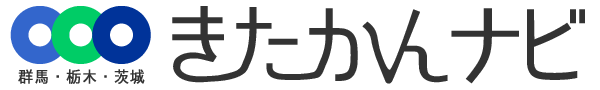 北関東を感じる観光情報サイト
北関東を感じる観光情報サイト