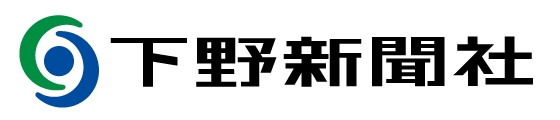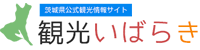思考と技術 昇華の足跡 特別展「加守田章二天極をさす」 益子陶芸美術館5月30日まで

20世紀後半の日本陶芸史に大きな足跡を残した加守田章二(かもだしょうじ)を約20年ぶりに回顧する特別展「加守田章二 天極をさす」が、益子陶芸美術館で開催されている。作家として頭角を現した益子時代に力点を置き、その再評価を試みるとともに、加守田が自身の造形思考と技術をどのように作品に昇華させていったのか、初期から晩年までの約130点でたどる。
一見すると、とても一人の作家の手によるものとは思えない。代表作「曲線彫文」シリーズとそれに続く彩陶以外にも、益子時代の須恵器のような灰釉、銀陶など多彩な作品が並ぶ会場で、あらためて「現代陶芸の旗手」と称された加守田の世界に圧倒された。
詩人高村光太郎(たかむらこうたろう)の「いくら廻(まわ)されても針は天極をさす」の一節から副題を取った同展。「高村光太郎賞」の賞牌(しょうはい)に刻まれたこの言葉は、加守田のために書かれたわけではないが、まさに彼の創作の核心を突いているという。
「加守田が行ったのは、うつわづくりではなく質感の制作」と同館の川北裕子(かわきたゆうこ)学芸員は解説する。素材から導かれる作意を土と焼成による陶の表現にどのように転換するか-。陶器の形態に造形、文様、質感の関係性を連動させようとした加守田の作風の展開は、テクスチャー(質感)の変遷に他ならないと指摘する。
確かに、時系列的に紹介されている作品をたどっていくと、ひし形や水玉などの好きなモチーフ、一貫して好んだ形や土肌の風合いなどが思わぬ形で反復されていることに気付く。
張りのある器体、鋭利な口づくりなど、加守田作品の特徴は益子時代から健在。同展は、さえざえとした青緑を求めて灰釉の仕事を突き詰め、作品を貫く美意識やスタイルの出発点ともなったこの時代に厚みを持たせ、大型作品に加え量産した皿や鉢にも焦点を当てている。釉調を追求した軌跡とともに、全体が浮遊したような底造りなど、ただならぬ雑器を構成する技術や美しさにも注目したい。
「灰釉鉢」で高村光太郎賞を受賞した頃、加守田は既に土器風の「酸化文」に移行していた。照りを嫌い焼成後に化粧土を剥がす焼締風の作品は、遺跡から掘り出されたような柔らかさとおおらかさ。北大路魯山人(きたおおじろさんじん)に触発されたという「銀陶角鉢」も照りとは無縁で、エッジの立った口、浮遊感のある底部など細部が光る。同時期に制作された「紫面鉢」の逆三角形と四角形から成る側面、ジーンズのような縁取りも新鮮だ。
この頃から遠野の土を使い始め、70年に「曲線彫文」を発表。翌年にはそれまでの無彩色から一転し「彩陶」と呼ばれる朱・白・緑の波状紋や水玉文様、鱗(うろこ)文が登場した。旺盛な制作意欲で次々と作風を広げていった加守田だが、緊張感のある造形と質感としての彩色への挑戦はどの作品にも通底する。
「やきものの範疇(はんちゅう)を超え、加守田作品は美術、デザインとして面白い。いつまでも古びない魅力がある」と川北さん。世界的な評価が高まる加守田作品の創造性を、プロセスから“体感”できる企画展になっている。
5月30日まで。入館は一般600円、小中学生300円。(問)同館0285・72・7555。
| 地図を開く | 近くのニュース |
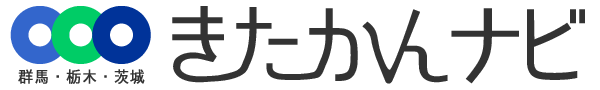 北関東を感じる観光情報サイト
北関東を感じる観光情報サイト