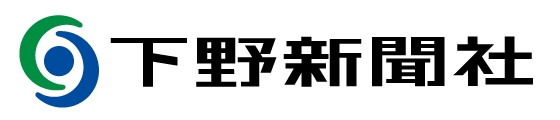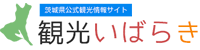有機大豆100%納豆 自社栽培、低価格化に対抗 茨城・土浦「ひげた食品」

納豆の一大産地である茨城県で、土浦市の納豆メーカー「ひげた食品」(塙裕子社長)が、自社栽培した有機大豆100%の納豆の製造販売に力を入れている。阿見町内で運営する畑の面積を拡大し、PRのため製品の直売会や催しも開く。担当者は「看板商品に育てていきたい」と展望。地産地消や安心安全をアピールし、「オンリーワン」の商品でファン獲得を図る。業界団体は「全国的にも珍しい取り組み」としている。
■コロナ特需も
同社は、同町上条にある約1・3ヘクタールの農場「のらっくす農園」で、ひきわり納豆に適した大豆「納豆小粒」と茨城県産大豆の在来種「たのくろ豆」を育てている。肥料には鶏ふんともみ殻を混ぜて使う。昨年の収量は計約750キロに上った。社員数人が農作業に従事し、雨などで作業できない日は工場で働く。
独自商品の開発にこだわる背景には、納豆業界の激しい競争がある。
コロナ禍の巣ごもり需要や、納豆に新型コロナウイルスの感染予防効果があるという研究が報道されると、納豆と縁遠い関西方面からも注文が寄せられた。「これまでで一番のブーム」(同社)だったが、感染拡大が落ち着くに連れ、従来の価格競争に状況が戻り、取引は減っていった。
塙武仁常務(37)は「大手は1パック100円を切るが、うちは3桁。価格では太刀打ちできない」と打ち明ける。営業先で門前払いされるなどの苦い経験を経て、他社に負けない看板商品づくりを意識するようになった。
■耕作放棄地再生
原料となる大豆の生産は壁が高かった。県内で有機大豆の委託生産を引き受けてくれる農家を探しても見つからない。そんな中、阿見町農業振興課の紹介で、元茨城大農学部教授の高原英成さん(72)と出会った。
高原さんは2000年、大学の地域貢献活動の一環として、町内の耕作放棄地を再生する実験農場を始めた。町内外の定年退職者らとともに、有機肥料を使って地力を回復させ、さまざまな野菜を育てた。近年はメンバーが高齢化で減少し、高原さん夫妻のみで農場を維持していた。
塙常務は高原さんを頼ろうと、直談判に訪れた。「ふかふかの土に一目ぼれした。ここならばおいしい大豆を作れると思った」と振り返る。高原さんも「自分たちにない新しいアイデアで活用してもらえるならば」と条件を付け、協力を決めた。
■地域交流拠点に
19年、同社は0・3ヘクタールほどの畑で有機大豆作りをスタート。20年には、収穫した大豆を使い、わらづと納豆を商品化した。
現在、畑では大豆以外にもトウモロコシやサツマイモを育てている。収穫祭や地元の園児を招いた食育体験会も開く。
塙常務は「農園を地域の交流拠点にしたい。原料生産から手がけた納豆として、会社の柱にしていく」と見据える。
全国納豆協同組合連合会(東京)によると、納豆メーカーによる有機大豆の自社栽培は全国的にも珍しいという。担当者は「有機はコンタミ(混入)の基準が厳しく、管理に手間がかかってコストもかさむため、大量生産には不向き」と課題を挙げつつ、消費者側からは「有機納豆には一定の需要がある」と指摘した。
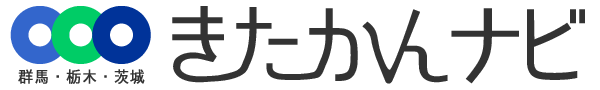 北関東を感じる観光情報サイト
北関東を感じる観光情報サイト