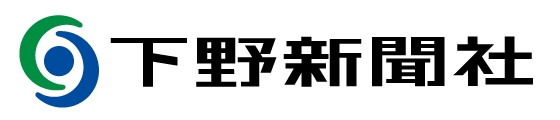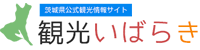清宮質文生誕100年展 県近代美術館 水彩の旋律 永遠の美

透明水彩を用いて深遠な内面世界を表現した本県ゆかりの木版画家、清宮(せいみや)質文(なおぶみ)(1917~91年)。郷愁を誘う木版を中心に、水彩画やガラス絵などを集めた大規模な回顧展「生誕100年 清宮質文 あの日の彼方へ」が、県近代美術館(水戸市千波町)で開かれている。創作の原点となったのが戦争体験。親しい人々を失った清宮の悲しみは、理想の高みを追う者の孤独へと重ねられ、永遠の美として昇華されている。
清宮は、画家で版画家だった父、清宮彬(ひとし)と雪江の長男として東京に生まれる。東京美術学校で油絵を学ぶが、油彩の立体表現がうまくいかず苦悩を続ける。幼い頃から父親の仕事を見ていたことも手伝い、軸足を版画へと移していく。戦後は、教員生活を経て、本格的に木版画に取り組む。54年から77年までは美術団体「春陽会」を発表の場とし、同会を離れてからは個展を中心に活動した。
また、先祖が、水戸藩支藩の守山藩(現在の福島県郡山市と大洗町の一部)藩士だったことや、祖父母の墓と母の実家が水戸の地にあったため、繰り返し同地を訪問。水泳が得意で那珂川で泳いだり、中学生の時には自転車で実家の東京・新宿から水戸まで旅したこともある。江戸っ子気質でありながら、「自分は水戸っぽ」と語るなど水戸を古里のように感じていた。
清宮が版画表現に求めたのは、版による複製性よりも、「彫り」の線や「刷り」による色の重なりといった版画ならではのおぼろげなタッチだった。インクは、油性ではなく透明水彩を用い、刷りごとに微妙に色調を変える作品には、見る者にそっと語り掛ける静かな詩情が漂う。
清宮はよく仕事を音楽に例えた。著書「雑感録」では、油彩をピアノに例え、「ピアノでバイオリンの音は出せない。多声のピアノに対して、バイオリンの一弦が奏でる旋律こそ水彩の心やすさだった」などとつづっている。
「清宮の版画の魅力は、シンプルに整理された線と悲しみをもった不思議な色彩。とりわけ、彫刻刀が作り出す線は、絵筆では決して出せない潔さがある」と同館の井野功一首席学芸員。「戦争体験が作風に通底している。清宮自身は戦地に赴いてはないが、徴兵された美術学校時代の友人の多くが外地で命を落としている。個人的な喪失体験を人間全体が背負った悲しみに置き換え、人の悲哀や郷愁を生涯のテーマにした」と話す。
同展では、木版を中心に、水彩やガラス絵など191点を紹介。蝶や猫、魚など身近なモチーフの作品が一堂に並ぶ。
黒を基調にした木版画「孤独な魂」は、強調された暗い目が不気味ながら、どこか悲しみをたたえているように見える。木版画「さまよう蝶(ちょう)(何処へ-夢の中)」は、遠い記憶に向かって漂流する魂の気配が感じ取れる。川面から顔を出すいくつもの目玉を表現した木版画「ながれ」は、連綿と受け継がれる生命の輪廻(りんね)を示唆しているようだ。
ガラス絵は、暗闇にほのかに輝くろうそくや、野に沈む夕日などを題材に、独特の透明感で描かれている。「窓辺の燭台(しょくだい)」「夜明け」「夕」などが並ぶ。ほかに、版木や作品の試し刷り、愛用の画材や道具も展示されている。
井野学芸員は「作品は身の回りの題材を主にしているが、その奥にある清宮の無限の内面を味わっていただければ」と呼び掛けている。
会期は4月8日まで。月曜休館。問い合わせは同館(電)029(243)5111。
【写真説明】「さまよう蝶(何処へ-夢の中)」=1963年、県近代美術館照沼コレクション
| 地図を開く | 近くのニュース |
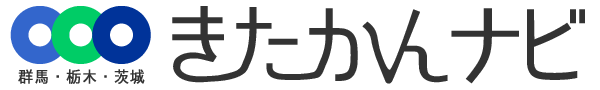 北関東を感じる観光情報サイト
北関東を感じる観光情報サイト