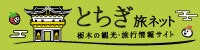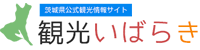時代映す華やかひな人形 江戸から昭和期 慶喜幼少期エピソードも 水戸市立博物館 茨城

茨城県水戸市大町の市立博物館で、特別展「人形百花譜~雛(ひな)人形を中心とした節句人形たち~」が開かれている。江戸後期から昭和期のひな人形をはじめ、浮世人形、五月人形、羽子板など約640点が並ぶ。徳川慶喜も幼少期に触れたというひな人形にまつわるエピソードも紹介し、華やかな空間を演出しながら時代を反映した人形の姿を伝えている。同展は3月9日まで。
同館によると、3月3日の桃の節句に行われるひな祭りは草木や紙、わらで作った人形(ひとがた)や形代にけがれを移して海や川に流すはらいの行事と、平安時代の人形遊びに当たる「ひいな遊び」が結び付いたとされる。同展はひな祭りの起源に触れ、男子の節句として広まった5月5日の端午の節句についても、こいのぼりや武者人形の展示を通じて説明している。
江戸中期の享保年間に作られ、明治期まで流行した「享保雛」や、京都や大阪で隆盛し、御殿にひな人形を並べた「御殿雛」などのほか、昭和の十段飾り、現在も手芸で親しまれているつるし雛、愛らしい犬張子を形状やテーマに分けてそろえた。
このほか、水戸藩9代藩主の徳川斉昭の子で15代将軍の徳川慶喜が幼少期に七郎麿(まろ)と呼ばれていた頃、ひいな遊びを通じた兄弟の様子を記した書物を紹介。水戸藩士の渡辺喜助が記録した「徳川慶喜公御幼少ノ日記」で、兄で後に鳥取藩主の池田慶徳となる五郎麿が準備した飾りを七郎麿が壊してけんかになったことが記されており、当時の慶喜の性格をうかがわせる展示となっている。
同館の小野瀬永子学芸員は「ひな人形は時代を映したようなところがあり、違いを見比べてみるのも面白いかもしれない」と話している。
月曜と2月25日休館で、午前9時半~午後4時45分。入場料は一般200円。
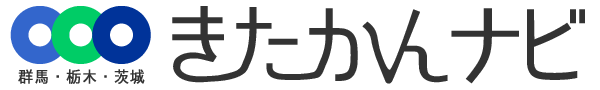 北関東を感じる観光情報サイト
北関東を感じる観光情報サイト