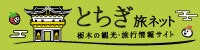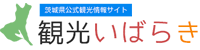ヘラブナ 水温で餌工夫 古河・管理釣り場 冬の1匹、うれしさ格別 茨城

日中は暖かい日も増えてきたが、水温は低く水中はまだ冬。それでも暖かい日は魚も春を感じるのか少し動きが良くなってくる。今回は四季を通して釣り方が変わる管理釣り場のヘラブナを紹介したい。茨城県古河市の管理釣り場「三和新池」へ釣行した。
ヘラブナは活性によって釣り方が変わる。冬は餌を吸い込む力が弱いため、寄せるバラケ餌と吸い込ませやすい食わせ餌のウドンを使うウドンセットが中心になる。水温が少し上がると餌を吸い込む力も徐々に強くなり、グルテン餌が釣りやすくなってくる。
釣行当日はヘラブナの活性が分からないので、バラケ餌と食わせにグルテンを使用したグルテンセットの底釣りを選択した。

林下桟橋から西桟橋を望む=古河市尾崎
釣り座は短いさおでも底が取れる「林下桟橋」へ入った。さおは13尺、バラケ餌は少し重いダンゴ餌をブレンドし、食わせ餌にはマルキュー新製品の「もちグル」を用意した。
底釣りは水深を測る棚取りが釣果に大きく影響する。そのため私は時間をかけて、丁寧な棚取りを心がけている。
準備が整い釣り開始。バラケ餌とグルテン餌を針に付けて打っていく。水温が低いので、浮きは打ち始めからすぐには動かない。まずはヘラブナを集めることを意識しながら、浮きのわずかな動きも見逃さぬようテンポ良く一定のスピードで餌を打っていく。
しばらくすると浮きがふわふわと動き出す。ヘラブナが寄ってきた証拠だが、浮きが明確に動く「アタリ」までは出てこない。
ヘラブナの食わせ餌への反応はアタリにつながるのだが、まだ餌の周りに寄っているだけ。食い気のあるヘラブナを呼び込むため、さらに餌を打ち返していくと、浮きがチクッと鋭く沈む動きが出る。待望のアタリである。
アタリに反応してさおを合わせると、ギュギュンとさおが大きく弧を描く。ゆっくりとさおを立てながら寄せてくると、25センチぐらい、きれいな魚体のヘラブナだった。数釣りは難しいのでうれしさは格別である。
餌打ちを再開すると、浮きの動きも良くなりアタリも増えてきた。しかし、アタリが出てもヘラブナが針がかりしてこない。誰もが経験する「カラツン」だ。
カラツンを回避すべく餌や棚取りを調整していくと、また針がかりするようになった。少しの改善で釣れるようになるのが、ヘラブナ釣りの難しさであり楽しさでもある。日中はさらに気温が上がりヘラブナの動きも良くなったことで、アタリが続き、釣果に恵まれた。(上州屋水戸店・小田木修)
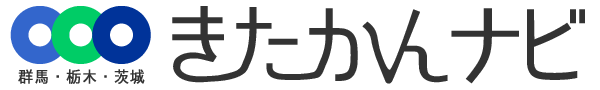 北関東を感じる観光情報サイト
北関東を感じる観光情報サイト