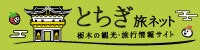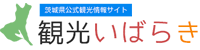近現代の暮らし回想 故会沢忠さんの絵展示 7月7日まで 茨城・常陸大宮

明治、大正、昭和の生活風景がよみがえる「記憶画に描かれた常陸大宮の暮らし」展が、茨城県常陸大宮市中富町の市歴史民俗資料館で開かれている。同市山方地区の諸沢出身の故会沢忠氏(1904~86年)が、色紙180枚に描き残した古里の暮らしや行事などの様子を展示。民具類とともに、同市の近現代の暮らしぶりを振り返る。同展は7月7日まで。
会沢氏は旧諸富野村に生まれ、農家手伝いの後、日立鉱山で働いた。退職後は帰郷し郵便局に勤め、絵を描くようになった。地域の暮らしを描写した作品を自費出版し、山方町誌でも取り上げられ、当時を知る貴重な資料となっている。
今回、取り上げている記憶画は、昨年10月に発刊された「常陸大宮市史資料叢書2 近現代1 描かれた常陸大宮の暮らし」(A4判、160ページ、1500円)に収められている。
題材は万能と呼ばれるくわを手にした田起こし、馬を引いて行った代かきなど、山々を背景に手作業だった稲作。そのほか、同地区の中島藤右衛門が発明した、こんにゃく芋を粉にする貯蔵法や、同地区特産の伝統和紙「西ノ内紙」の紙すき、久慈川の渡し船、諸富野小学校から袋田の滝までの徒歩遠足、アユ漁解禁などさまざま。
市史編さん委員会専門調査員の清水ゆかりさんは「絵に描かれた人々の暮らしは、地域の人々の集合的記憶。彼らの血のにじむような努力が現在の豊かな暮らしにつながっている、と後世に伝えるため、会沢は記憶画を描いた」と述べている。
開館は午前9時~午後4時半。月曜・祝日休館。無料。
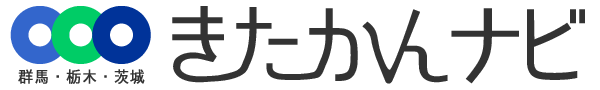 北関東を感じる観光情報サイト
北関東を感じる観光情報サイト