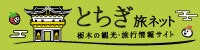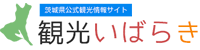北茨城の歴史ひも解く 市歴史民俗資料館で特別展 平潟港、常磐炭鉱 絵画や古文書

茨城県北茨城市の歴史の中から特徴的な事柄を紹介する特別展「HISTORY OF KITAIBARAKI CITY」が、同市磯原町磯原の市歴史民俗資料館で開かれている。市制施行70周年を記念し、企画。絵画や古文書など34点が展示され、戊辰戦争時の平潟港や「大津浜異人上陸事件」、かつての基幹産業・炭鉱など地域を彩った記憶がよみがえる。12月7日までの期間中は入館無料。
会場には同市平潟町の平潟港を題材にした作品が多く並ぶ。同港は江戸時代、東北地方の藩が年貢米などを収めるために使った「東廻(まわ)り航路」の寄港地として発展。明治時代に描かれた「平潟港絵図」には多くの商船が描かれており、現在の漁港とは違った役割があったことをうかがい知ることができる。
明治時代に活躍した五百城文哉(いおきぶんさい)が平潟港を描いた油彩画も展示。戊辰戦争時、奥羽越列藩同盟の盟主に擁立された輪王寺宮(りんのうじのみや)(北白川宮能久親王)が東北に逃げる際に帰港した様子を後年に描いており、日本の転換点の一端に触れられる。同港を囲む自然や美しい湾曲を切り取った風景画もある。
さらに、大正時代に複製された横山大観の大作「生々流転」も並ぶ。その一幕に描かれた桟橋や港を平潟港とする説があり、合わせて展示した当時の写真との比較が楽しめる。
加えて、「鎖国」下の江戸後期、同市の大津浜に外国人が上陸し、幕府に動揺が走った一大事件を記録した文書「異国船上陸記」も展示。イギリス人の上陸から帰国までの状況が書かれた貴重な資料が並ぶ。
近代からは同市の経済や戦後復興を支えた「常磐炭鉱」の絵画を展示。同市にはかつて多数の鉱山があり、石炭輸送のために敷設された常磐線で重要なエネルギーを首都圏などに供給していた。今回は磯原町にあった「重内の洗炭所」や中郷町の「中郷抗」の街並みを描いた作品がそろい、当時の面影を伝える。
このほか、童謡詩人・野口雨情の先祖が徳川光圀から授与された茶わんとその由緒を雨情がしたためた書物、同市中郷町日棚の細原遺跡から出土した市内最古の石器、市ゆかりの画家が描いた現代の風景画も一堂に会する。合わせて、日展入選作品4点も飾られ、会場に花を添えている。
開館は午前9時~午後4時半(入館同4時まで)。原則、月曜休館。
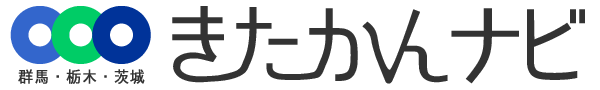 北関東を感じる観光情報サイト
北関東を感じる観光情報サイト