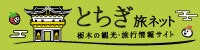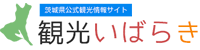武具彩る雪華結晶 藩主、土井利位の愛用品展 古河歴史博物館 茨城

江戸後期の1832(天保3)年に日本で初めて雪の結晶を観察した図鑑「雪華図説(せっかずせつ)」を著したことで知られる古河藩主、土井利位(としつら)(1789~1848年)愛用の刀剣や刀装具を展示する企画展が、茨城県古河市中央町の古河歴史博物館で開かれている。当代一流の名工の技術を集めて「雪華(ゆきはな)」の模様を施した刀や刀装具の一式が博物館の所蔵品として展示されるのは初めて。同展は5月6日まで。
展示の目玉は大小の刀一式。利位が江戸幕府の老中を務めていた1841年に作らせた。当時、全国の大名家から注文が殺到したという人気の刀工、固山宗次をはじめ、京都の金工、後藤一乗や後藤真乗、彫金師の浜野政信、鉄砲鍛冶で発明家の国友一貫斎ら、そうそうたる職人が制作に関わった。刀を収める鞘(さや)や鐔(つば)、柄頭(つかがしら)といった刀装具には、繊細な雪の結晶模様が、彼らの手で精巧に表現されている。

雪華模様が施された刀装具
同博物館の永用俊彦学芸員は「利位は雪華模様を工芸品などに取り込んで流行を生み出し、自身や古河藩の存在感を高めることにも成功した。ただ利位が直接手がけた品々のほとんどは戦争や震災などで失われた。刀と刀装具の一式がそろって残っているのは奇跡に近い」と話す。
刀一式は国内の愛好家が所有していた。市は愛好家が亡くなった後も遺族と交渉を続け、2024年3月に購入できたという。
永用学芸員は「当時集め得る職人のコラボで生まれた名品。利位や古河藩の人脈や交渉法などを知る上でも貴重」と話す。
同展では制作に携わった名工たちの作品も紹介している。問い合わせは同博物館(電)0280(22)5211。
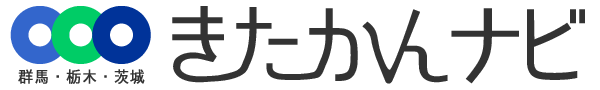 北関東を感じる観光情報サイト
北関東を感じる観光情報サイト