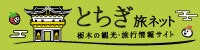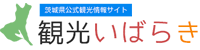《戦後80年》兵事史料で世相学ぶ 常陸大宮市文書館が企画展 茨城

茨城県常陸大宮市北塩子の市文書館で、企画展「戦後80年 資料が語る戦争の記憶」が開かれている。戦後80年の節目に、現存するわずかな兵事史料、市域に関係する戦争資料を基に、戦争と地域社会の結び付きを紹介している。残された貴重な行政文書を中心に、戦時中の世相を明らかにしている。
満州事変(1931年)から終戦までの15年間で、日本人の国内外での戦没者は300万人以上と推測される中、同市域でも2100人超の尊い命が戦病死し、失われたとの記録が残る。当時の村町役場には兵事係があり、召集を待つ在郷軍人や徴兵の管理・動員など、戦争と密接に関わる業務を担当していた。
展示では、兵事業務の一端について触れている。戦前の大日本帝国憲法で規定されていた兵役の義務や徴兵検査、召集令状などについても解説。出征や戦没者の村葬(町葬)による慰霊の様子など、当時の写真とともに紹介している。
ほか、市域からも75人が出征し犠牲となった激戦地のペリリュー島の戦い、彼らが所属した水戸歩兵第二連隊に関する資料、将校団の寄せ書きなども展示している。
9月上旬には、水戸歩兵第二連隊の団旗(複製)、ペリリュー島の遺品などが追加展示される。
同館では「この戦争は地域社会と密接に関係し、多くの兵士が戦地へと動員されたが、その実態はどういうものだったのか。常陸大宮市域に関連する戦時資料の中から、戦時中の人々の暮らしや兵事業務の一端を知ってほしい」と話す。
展示は11月9日まで。入場無料。午前9時~午後4時半。月曜・祝日休館。9月6、20日、10月4、18日、11月8、9日には展示解説(午後2時から約1時間)がある。
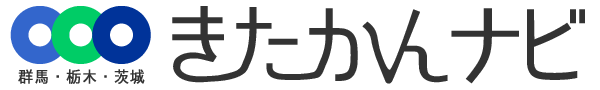 北関東を感じる観光情報サイト
北関東を感じる観光情報サイト