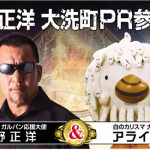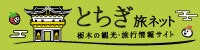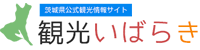「ご先祖」弔う風習紹介 土浦市立博物館で企画展 江戸から明治、魔よけ道具や霊きゅう車 31日まで 茨城

江戸から明治にかけて、亡くなった人を弔う風習や先祖との向き合い方を紹介するテーマ展「ご先祖さま 弔う・迎える・期待する」が31日まで、茨城県土浦市中央の市立博物館で開かれている。想像上の動物「獅子」を模した魔よけの道具や人力の霊きゅう車を展示したほか、民俗行事の「盆綱」を紹介している。
高さ約2メートルの竹を使った魔よけの道具「シシテンゲ(獅子天蓋)」は、集落で人が亡くなった際に葬列を先導した。竹製の「蛇腹(じゃばら)」も用いられた。常名地区には「オオカミよけ」として伝わり、いずれも昭和期に使用されたという。
棺おけを乗せて墓地まで人力で引く霊きゅう車も展示された。乙戸地区で1955年から使われた後、同館に寄贈された車体には、棺おけを納めるみこしが乗っている。神道を表す鳥居と仏教を表す「卍(まんじ)」の両方のシンボルが彫られている。
佐野子地区に伝わるお盆の行事「盆綱」も紹介し、ヘビを模した約3メートルの綱を展示した。子どもたちが綱を担ぎ、墓地と集落の家庭を訪れる映像も流す。先祖を綱に乗せ、各家庭に届ける意味が込められているという。
展示の後半は、江戸時代に土浦藩を治めた土屋数直の先祖、昌続が武田信玄らと共に描かれた絵画や家系図、書状といった資料が並ぶ。藩から重用されて年貢を免除されたなど、後世の人物が先祖への期待を込めて史実と異なる内容を記した「偽文書」も展示している。
担当した西口正隆学芸員は「一番身近な歴史でもあるご先祖さまを振り返る機会になれば」と来場を呼びかけている。
午前9時~午後4時半。入館料は一般200円、高校生以下無料。問い合わせは同館(電)029(824)2928。
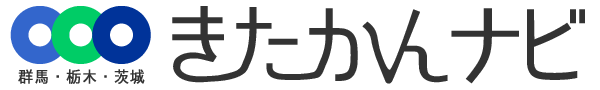 北関東を感じる観光情報サイト
北関東を感じる観光情報サイト