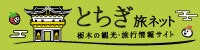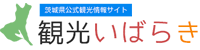《戦後80年》日立の戦災たどる 兵士の手記や軍服 市郷土博物館 茨城

戦時中に茨城県日立市内であった空襲などの戦災や市民の生活を展示する「昭和の戦争」ギャラリー展が、同市宮田町の市郷土博物館で開かれている。戦後80年を迎え、当時軍需工場が集まっていた日立の様子を写真と資料でたどった。戦争で亡くなった兵士の手記や軍服、身の回り品も並べ、多様な視点から戦争を考える内容になっている。同展は7月27日まで。
展示された写真約40枚は、市民らから提供され、戦争に駆り立てられる市民の姿を知ることができる。
大甕駅での1枚は、応召された軍人を祝い事のように盛大に見送る様子を写し出した。一方、中国戦線で戦死した軍人は市による合同葬儀が厳かに執り行われた。ほかに少年による警防団、高台にあった防空監視や演習の光景は非常時の雰囲気を伝える。軍需工場だった日立製作所では、学徒たちが工員としての実習を受け、女性だけで労働する女子挺身(ていしん)隊が駆り出された。工場の電気部品は子どもたちによって学校の教室でも作られ、「学校工場」と呼ばれた。
日立市は度重なる空襲と艦砲射撃で1500人以上の市民が死亡した。壊滅した工場や焼け野原となった市街地の写真は、戦争の悲惨さをあぶり出している。
戦死した遺族から提供された遺品も初めて展示された。同市内の河原子出身の梅原伊智郎さんは1932年、満州で陸軍に入隊。中国軍との戦闘を経て、36年、病気のため24歳で亡くなった。満州国軍の軍服と帽子、手帳のほか、上海にいた弟や日本の家族に宛てた手紙も並べた。
大和田兼松さんは中国戦線で25歳で戦死。本人の肖像写真や軍用の手帳、軍票のほか、死後の遺骨到着通知や葬儀の弔辞といった資料も展示した。
同館では「資料を通じて平和の大切さを感じてもらえれば」と来場を呼びかけている。入場無料。
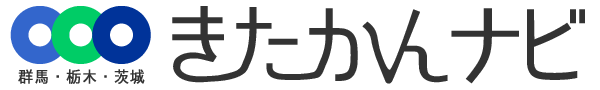 北関東を感じる観光情報サイト
北関東を感じる観光情報サイト